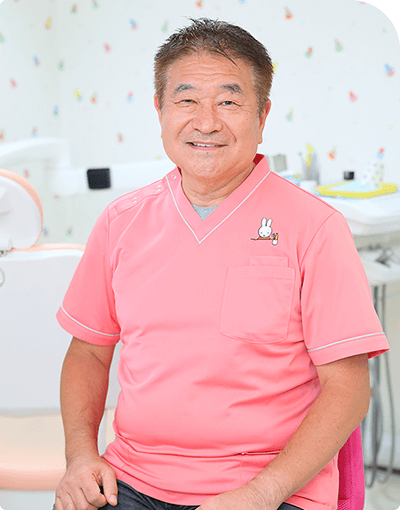子どもの歯並びが悪いと、親としては心配になりますよね。歯並びの問題は見た目だけでなく、噛み合わせや発音、さらには全身の健康にも影響を及ぼすことがあります。
この記事では、子どもの歯並びが悪くなる原因となる悪習慣について、詳しく解説します。
目次
■歯並びが悪くなる習慣、癖や行動って?
◎指しゃぶり
指しゃぶりは多くの子どもが経験する自然な行動ですが、長期間続くと歯並びに悪影響を及ぼすことがあります。
特に、前歯が前方に突出する「出っ歯」や、上下の前歯が噛み合わない「開咬(かいこう)」と呼ばれる状態になることが多いです。
指しゃぶりはお子さんの歯並びの状態にもよりますが、一般的には3~4歳頃までには止めさせるのが理想です。
◎口呼吸
口呼吸は、鼻が詰まっている場合や、癖で口を開けたまま呼吸している状態です。口呼吸が続くと、顔の筋肉や舌の位置が正常な発育を妨げ、歯並びに影響を与えることがあります。
特に、上顎が狭くなる「上顎狭窄症(じょうがくきょうさくしょう)」や、歯が重なり合う「叢生(そうせい)」の原因となります。
◎舌の位置
舌の位置が正しくないことも歯並びに悪影響を及ぼします。正常な舌の位置は、上あごの前歯の裏側に軽く触れている状態です。
しかし、舌が下あごに位置していると、前歯が前方に押し出されることがあります。これにより、出っ歯や開咬が引き起こされることがあります。
◎長期間の哺乳瓶使用
哺乳瓶の長期間使用(特に3歳以降も続けている場合)は、歯並びに悪影響を及ぼすことがあります。
哺乳瓶を吸う際の強い吸引力が前歯を前方に押し出し、出っ歯の原因となることがあります。また、口の周りの筋肉の発達にも影響を与えることがあります。
◎不適切な食生活
柔らかい食べ物ばかりを食べることも、歯並びに影響を与えることがあります。
バランスよく硬い食べ物を噛むことで、顎の筋肉や骨が正常に発達し、歯が正しい位置に並ぶことが期待できます。柔らかい食べ物ばかりを食べると、これらの発達が妨げられ、歯並びが悪くなる可能性があるのです。
■歯並びの改善には早期対策が重要
子どもの歯並びに不安を感じたら、早期に対策を行うことが大切です。早期に歯科医師・歯科衛生士に相談することで、適切な時期・治療や、トレーニングを受けることができます。
また、上記の悪習慣を改善することで、歯並びの問題を未然に防ぐことができます。
■MFT(口腔筋機能療法)の重要性
MFT(口腔筋機能療法)とは、お口の周りの筋肉を正しく機能させるためのトレーニングです。これにより、歯並びが悪くなる原因となる悪習慣を改善することができます。特に、舌の位置や口呼吸の改善に効果的です。
MFTのトレーニング方法や詳細については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【子どもの歯並びを悪化させる癖は早急に治しましょう】
子どもの歯並びが悪くなる原因は、指しゃぶりや口呼吸、舌の位置、長時間の哺乳瓶使用、不適切な食生活などの悪習慣が関与しています。これらの習慣を早期に改善することで、歯並びの問題を防ぐことができます。
また、MFT(口腔筋機能療法)を取り入れることで、さらに効果的に噛み合わせ・歯並びの改善が期待できます。子どもの健康な歯並びを保つために、日頃の習慣を見直し、必要ならば当院の歯科医師・歯科衛生士までご相談ください。